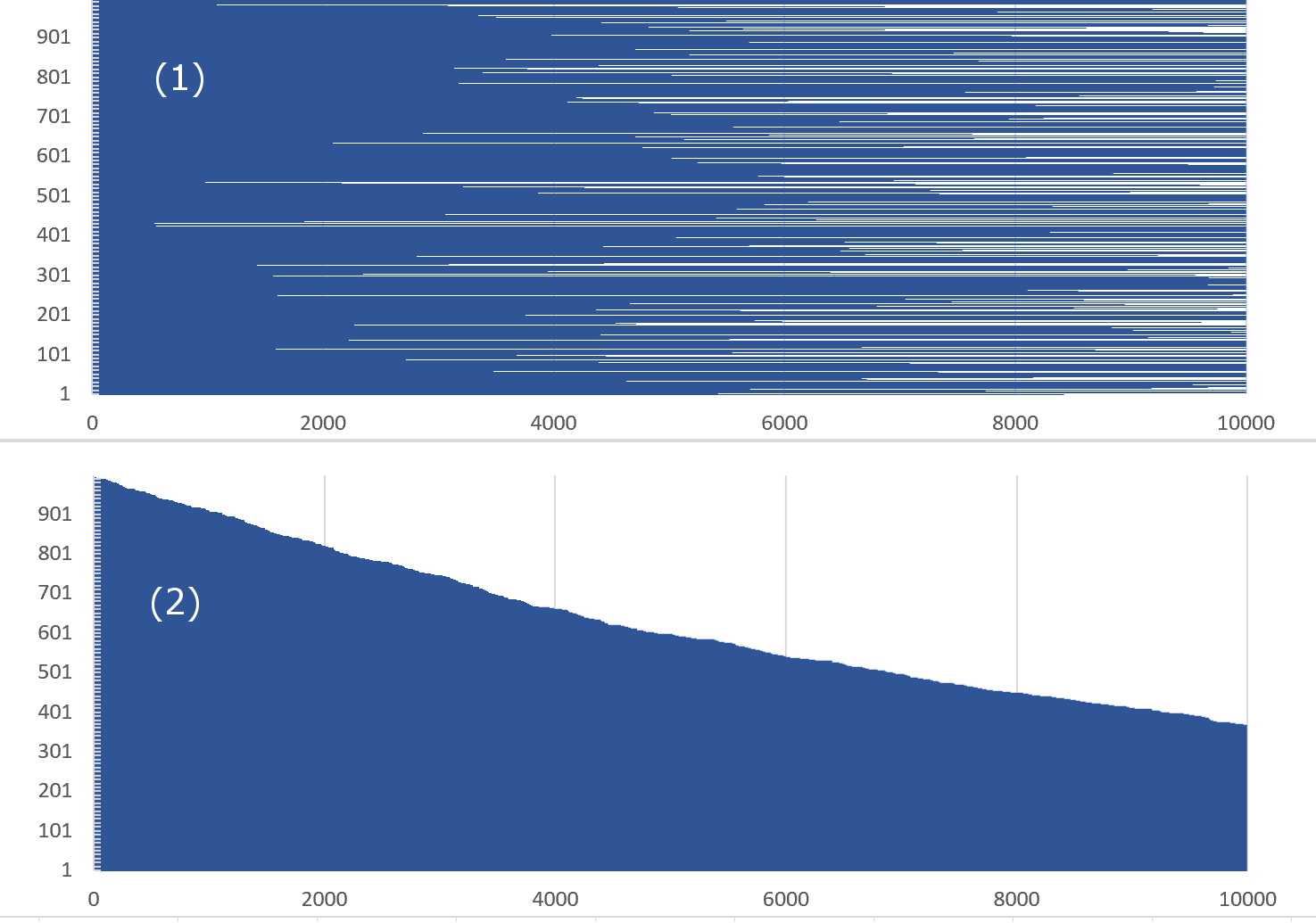|
3 |
確率論 (9) |
 |
基本単位
- $\Omega$の部分集合の族$\mathcal{G}$が$\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$を満たし、かつ$\mathcal{G}$自身が$\sigma$加法族であるとき、$\mathcal{G}$を$\mathcal{F}$の部分$\sigma$加法族という。
- $\sigma$加法族$\mathcal{G}$の要素集合$A(\neq\varnothing)$で、$A$自身と$\varnothing$を除く全ての$A$の部分集合が$\mathcal{G}$に属さないとき、$A$を$\mathcal{G}$の基本単位という。
基本単位は情報の粗さを決定する最小単位です。例を挙げてみます。
標本集合 $$ \Omega=\{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}, \img[-0.2em]{/images/d2s.png}, \img[-0.2em]{/images/d3s.png}, \img[-0.2em]{/images/d4s.png}, \img[-0.2em]{/images/d5s.png}, \img[-0.2em]{/images/d6s.png}\} $$ があり、どのような基本単位で事象を考えるかについて、例えば、$\sigma$加法族$\mathcal{F}$に関して、 $$ A_1=\{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}\}, A_2=\{\img[-0.2em]{/images/d2s.png}\}, A_3=\{\img[-0.2em]{/images/d3s.png}\}, A_4=\{\img[-0.2em]{/images/d4s.png}\}, A_5=\{\img[-0.2em]{/images/d5s.png}\}, A_6=\{\img[-0.2em]{/images/d6s.png}\} $$ のような集合$A_i (i=1,...,6)$を考えると、これは上記の基本単位の定義を明らかに満たしています。 各事象集合$A_i$に属する集合は根元事象で、その部分集合から自分自身と$\varnothing$は無いため、$\mathcal{F}$に属さず、$A_i$は$\mathcal{F}$の基本単位となります。
次に、奇数の目の集合と偶数の目の集合を考えます。 $$ A_\text{odd}=\{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}, \img[-0.2em]{/images/d3s.png}, \img[-0.2em]{/images/d5s.png}\}, A_\text{even}=\{\img[-0.2em]{/images/d2s.png}, \img[-0.2em]{/images/d4s.png}, \img[-0.2em]{/images/d6s.png}\}, \mathcal{G}=\{A_\text{odd}, A_\text{even}, \Omega, \varnothing\} $$ 自分自身と$\varnothing$を除く$A_\text{odd}$の部分集合は、 $$ \{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}\}, \{\img[-0.2em]{/images/d3s.png}\}, \{\img[-0.2em]{/images/d5s.png}\}, \{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}, \img[-0.2em]{/images/d3s.png}\}, \{\img[-0.2em]{/images/d1s.png}, \img[-0.2em]{/images/d5s.png}\}, \{\img[-0.2em]{/images/d3s.png}, \img[-0.2em]{/images/d5s.png}\} $$ となり、いずれも$\mathcal{G}$に属していません。$A_\text{even}$に関しても同様であり、$A_\text{odd}$、$A_\text{even}$とも、$\mathcal{G}$の基本単位となります。
この例は、確率微分方程式とその応用, 清兼泰明, 森北出版の例2.3.10に掲載されているものです。